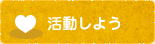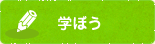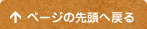仏教者の活動紹介
カルトにひきこもらないで ―大明寺―
(ぴっぱら2004年4月号掲載)
伝統とともに
神奈川都民などという言い方もあるけれど、やはり地元は地元としてきちんと根付いている。JR横須賀線を終点の一つ手前で降り、衣笠大通の商店街を歩きながら、そう感じた。どこでも見かけるスーパーのチェーンが大きな顔をしていることもなく、地元の商店街が生き生きしている。どこかでブラスバンドが練習しているらしく、聞き覚えのある音楽が聞こえてくる。その音をたどるように歩くと、高校の校舎の手前に長い石段が見えた。日蓮宗の大明寺だ。
大明寺は、立教開宗を宣言した日蓮上人にいち早く帰依し、上人を支え続けた石渡則久夫妻に由来する伝統深い寺院だ。廃仏毀釈により放火されて一度失われたものの、明治後期に再建された本堂を中心に、広い境内が街の人々に安らぎを与えている。
犬を連れたおばあさんが、なだらかな石段の脇でひと休みしていた。会釈しながら石段を昇りかけると、まだ新しい看板が植え込みの中から顔を出しているのに気づく。「青少年こころの相談室」。訪ねてくる人をあたたかく招き寄せるように、参道に植えられた梅の木から、花の香が漂っていた。
宗門として 寺院として
日蓮宗の歴史と共にあるような寺院だが、その活動は伝統に縛られてはいない。日によっては一日二桁の件数の法要を執り行う一方で、宗門が支援する社会福祉法人の本部相談室「青少年こころの相談室」としての顔も併せ持つ。
昭和50年代半ば、非行やいじめ・校内暴力など子どもの問題が表面化しだした頃。日蓮宗宗門の中で「将来を担う青少年のために宗教者として必要なことをすべきなのでは」という声が高まった。しかし、お寺はすでに一般の人には敷居の高い場となってしまっている。そこで、宗教法人としてでなく、敢えて社会福祉法人として青少年のためのプロジェクトがスタートした。
現在、社会福祉法人「立正福祉会」として教育や社会活動に対して助成を行う一方、全国の各管区1つを目安に32の機関相談室と、120の分室が設置され、さまざまな相談を受けている。相談料は無料(実費のみ)。経費は相談室連絡協議会という組織に宗門と各寺院が支出した基金をもとに、各相談室に資金が分配されて運営されている。
大明寺におかれているのは、機関相談室とは別に設置された本部相談室だ。相談を受けるだけでなく、月1回の研修会や事例研究・実践を通して相談員の育成も行っている。
手紙や電話・インターネットを介して寄せられる相談は年間2000件を越える。それらの相談に3人の僧侶や大学院を卒業した青年、もと相談者の若者たち計10人とともに対応しているのが、住職の楠山泰道さんだ。
楠山さんは、もともとは高校で教師をする一方、大明寺の末寺である妙伝寺の住職として相談室の分室を運営していた。その後、大明寺の住職として任命を受けた楠山さんは、妙伝寺と相談室を息子さんに任せて大明寺に移る。その楠山さんのもとに本部相談室が開設されて現在に至っている。
非行もカルトも同じ
妙伝寺時代、楠山さんは当初非行や暴走族の少年などの対応をしていたが、統一協会を脱会したいという相談を受けたのをきっかけに、横須賀のキリスト教会の中にある統一協会被害者の親の会から、「オウムについて相談を受けているが、仏教のことはよくわからないので......」と連絡を受け、オウム問題にかかわるようになった。
それ以来大明寺に移った現在も、相談のほとんどがカルト問題だ。JDCC(日本脱カルト研究会)設立に携わり、その理事も勤めるなど、楠山さんはいまや、カルト問題と向かい合う仏教者としていまや知る人ぞ知る存在となっている。他に、不登校を含むひきこもりや、価値観の多様化の中で進路に関しての悩み、自殺したいという相談も年十数件あるという。
「非行もひきこもりもカルトの問題も、根は同じなんです」と語る楠山さん。いずれの場合も、家族のきずな、他者とのきずなを得たいのに得られず苦しんでいるからだ、と。その苦しみの中で他者や社会との関わり方を見失ったときに、その苦しみが非行やひきこもりという形で表れ、あるいはカルトにつけこまれてしまうのだ。
カルトにひきこもらないで
そんなふうに「自分が見つからない」と迷ったとき、人とのかかわり合いがわからなくなったときに宗教にその答えを求めるのは本来は自然なことだと楠山さんは語る。
だがなぜそこで若者たちは既存の宗教ではなく、カルトに答えを求めてしまうのか。「(既存の)宗教が役割を果たしていないからです」と楠山さんは断言する。宗教は本来、生きている間と死後、双方の心の癒しをすべきなのに、宗教者は儀式などの形で「死後の癒し」だけを強調してきた。そこに「生の癒し」を語るカルトが現れ、安易に答えを与えて一時的に癒してくれるのだ。悩む若者は「生の癒し」を求めているのだから、そちらに惹かれてしまうのは当然かもしれない。
「その癒しから抜け出して、社会の中で自立していけるようにしなければ本物の救済ではない。それなのに『依存していなければ救われない』と言うのがカルトなんですね」
カルトに依存した状態でありながら、そこで「自分を発見した」と思ってしまう。カルトでつくられた自分を本当の自分だと思ってしまい、それを批判する社会とかかわりを持たなくなってしまう。「カルトにひきこもってしまうんです」という楠山さんの言葉は、若者たちの状態をとてもよくあらわしているように感じられた。
お寺もひきこもらないで
今後、カルトによる被害への予防・啓蒙活動や実際のカルトへの対策だけでなく、ノウハウを伝えていくことを行っていきたいと楠山さんはいう。また、「オウムの信者が語った言葉を覚えてますか?『お寺には宗教がない』ですよ。それに対して『ふざけるな!』と言える仏教者がどれだけいるか。宗教者は本来の役割を取り戻し、宗教活動に戻るべきです。これからの社会に必要な宗教とは何なのか?と問いかけていきたいですね」
寺院離れ・仏教離れが叫ばれる中、それを懐手して眺めていても始まらない。かといって、何をすればいいのかわからない。そんな僧侶たちへのメッセージと言えるだろう。
「お寺も"ひきこも"っている」とは、かつて全青協で開催したフォーラム参加者の名台詞だ。寺院や僧侶も、社会とのかかわりがわからなくなってひきこもったりカルトにはまったりして悩む若者たちとともに、もう一度社会とのかかわり・社会での自立を模索してみなくてはならないのではないだろうか。(内)