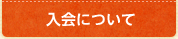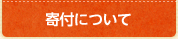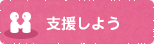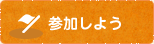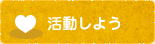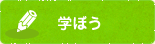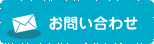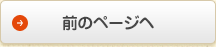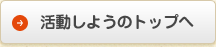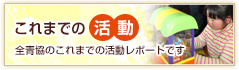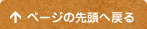正力松太郎賞
2025.10.01
第49回正力松太郎賞・あおぞら奨学基金記念式典を開催しました
9月29日、全青協は東京・港区の曹洞宗檀信徒会館にて「第49回正力松太郎賞・あおぞら奨学基金記念式典」を開催しました。正力松太郎賞受賞者の活動報告と表彰式に加え、東日本大震災をはじめとする被災地の高校生に返還不要な奨学金を供与する「あおぞら奨学基金」の功労者に対して、感謝状の贈呈が行われました。
正力松太郎賞受賞者としては、本賞を受賞した藤田佳子氏(淑徳大学教育学部客員教授・パネルシアター作家)、奨励賞を受賞した中野浄昭師(浄土宗浄泉寺住職・大分県国東市)、そして、特別賞を受賞した吉岡秀人氏(特定非営利活動法人ジャパンハート最高顧問・小児外科医)および「公益社団法人 三宝(さんぽう)莚(えん)国際交流協会」(滋賀県大津市)の栢(かや)木(き)寛照理事長(善光寺本坊大勧進貫主)が出席し、賞状と副賞が贈呈されました。
▼▼ 受賞者それぞれの活動
表彰式に先立って行われた選考報告会では、正力松太郎賞受賞者が登壇し、映像などを交えてこれまでの活動について紹介がなされました。
本賞を受賞した藤田佳子さんは、1977年より、視聴覚コミュニケーション教材「パネルシアター」を通じて、仏教教育と仏教福祉活動に取り組んできました。パネルシアター創案者の僧侶、古宇田亮順さんのもとで研修を重ね、国内のみならず、アジア諸国や中南米でも子どもたちを楽しませるとともに、パネルシアターの導入活動を進めています。なお、古宇田さんは正力松太郎賞第5回(1981年)の受賞者であり、今回の受賞は師弟での受賞となりました。
藤田さんは、手遊びや歌を交えながら、たこやきの作り方を題材にしたパネルシアター「たこ焼きパクッ!」を実演。会場全体が温かな雰囲気に包まれました。藤田さんは2004年に発生したスマトラ沖地震の際には、スリランカの幼児教育施設や仮設キャンプを訪れ、非常時の子どもたちに、ひと時でも不安を忘れ、笑顔になれる時間を提供したいと活動しました。2011年の東日本大震災後には「パネルシアターキャラバン」として指導する学生とともに被災地を巡回し、奉仕活動を行いました。
「被災地で演じた時も、すぐに笑顔が広がりました。パネルシアターは簡単に作ることができて、子どもたちの発達や集中力、意欲を高めます。これからも広めていくための体制づくりや指導者育成に精進していきたいです」と、今後の抱負を述べました。
続いて登壇した奨励賞の中野浄昭さんは、戦前から「地域の寺子屋」として親しまれてきた浄泉寺において、農業体験、夏休みのラジオ体操、盆踊り大会など、多世代交流と仏縁の醸成に尽力してきました。選考報告会では、自作のビデオでこれまでの浄泉寺の歴史と活動を紹介しました。
本年は新たに、子どもや家族の防災意識を高め、地域コミュニティのつながりを深めることを目的とした防災イベント「あそび防災プロジェクトin浄泉寺」を企画、実施しています。中野さんは「過疎化で子どもが減っていますが、苦しい時こそ仏様の智慧を信じてきました。『困りごとがあれば浄泉寺へ』と言ってもらえるよう、これからも開かれたお寺として地域に尽くしていきたいです」と思いを語りました。
次いで、特別賞受賞者の吉岡秀人さんが登壇しました。吉岡さんは「医療の届かないところに医療を届ける」という信念のもと、1995年よりミャンマー等で無償の医療活動を続けてきました。2004年には「ジャパンハート」を設立。今年3月に起きたミャンマー地震の際にも、震源地近くの病院で自らが被災しながらも、現地で救援活動を行いました。
ミャンマーは、かつて大東亜戦争の激戦地で多くの日本人が命を落とした地でもあります。この時、傷ついた日本兵を助け、かくまってくれたのは他ならぬミャンマーの農家の人びとでした。ミャンマー人を助けることは、日本兵への慰霊ともなると考え、医療活動に邁進(まいしん)した吉岡さん。
「現地では朝から晩まで患者を診続けた。停電も多く、手術できずに患者を返すことが苦痛だった。活動を始めた頃と同じ病に、今も苦しみ、命を落とす人々がいる。生涯この活動を続けていかなければならない」と活動への思いを述べました。
同じく、特別賞を受賞した「公益社団法人 三宝莚国際交流協会」の活動については、理事長の栢木寛照さんより報告がありました。
同協会は1978年より、かつて太平洋戦争の激戦地だったサイパン島で、慰霊と平和をテーマにした青少年交流活動を実施しています。1982年からはサイパン島の青少年を日本に招く相互交流も行っており、戦争の記憶を風化させず、若い世代に平和の尊さを伝えることを目的に、国際的な視野を持つ青少年の育成に尽力してきました。これまでの参加者は、両国併せて二千人を超えています。
栢木さんは、サイパン島で戦没者を慰霊する灯籠流しを子どもたちとともに行った際の印象的な出来事を紹介しました。海に流した灯籠の光は、不思議なことに、二列になって日本の方角へ流れていきました。子どもたちはその様子を見て、「兵隊さんが二列になって日本へ帰っていくようだね」と話したということです。
「戦争を忘れないことが、戦争を起こさないことにつながる。子どもたちに、この思いを何とか引き継いでいかなくては」と平和への願いを強調しました。
▼▼智慧と慈悲の実践を目指して
祝賀会では、受賞者と共に「あおぞら奨学基金」のサポーターとして長年にわたり子どもたちを支援した功労者が登壇し、理事長より感謝状が授与されました。
あおぞら奨学基金は、震災翌年の2012年に全青協が立ち上げ、現在では関係二団体と協力しながら、経済的に困難な状況にあるご家庭の生徒を対象に奨学金を供与しています。奨学生の数は千名を超え、当基金の卒業生の中には、医療従事者や教員、プロスポーツ選手として夢を実現された方々もいます。
奨学生には、年に2回、近況をつづったお手紙を書いていただいており、学校と事務局を経由してサポーターに届けられています。
サポーターの中には、そのお返事としてお手紙を子どもたちにしたためてくださる方もいて、ある奨学生は「学校とアルバイトの両立がつらかった時もありましたが、サポーター様のお言葉で勇気づけられ、卒業まで頑張ることができました」と、感謝の弁を述べていました。
奨学金を供与する側、される側という関係性に留まらず、温かなこころの交流も実現している同事業を永く継続できればと思いを新たにした瞬間でした。
祝賀会は、正力松太郎賞受賞関係者と奨学基金の功労者の交流の場ともなり、席のあちらこちらで笑顔の花が咲いていました。
結びの挨拶として藤田佳子さんは、関係者の方々へ謝意を述べ、「パネルシアターは、楽しい! がキーワードです。これからも子どもたちのためにパネルシアターを実践し、研究を続けていきたいです」と述べました。
中野浄昭さんは、「うちは小さなお寺ですが、浄泉寺での活動を通じて、年長者を敬い、年少者を慈しみ、地域を愛する気持ちが自然に培われる場にしたいです」と今後の抱負を語りました。
地震や豪雨といった自然災害、世界各地での紛争や戦争による人びとの差別や分断、そして急速な温暖化の進行など、社会的な混迷は益々深まっており、心の拠り所が一層求められる昨今です。こうした中で、仏教の説く慈悲と智慧を、いかに現実社会において実践していけるかが問われています。
正力松太郎賞の受賞者の皆様、そして、あおぞら奨学基金サポーターの皆様の尊いご活動が、多くの仏教者の道しるべとなることを願ってやみません。