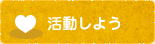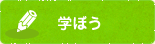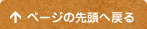- TOP
- 学ぼう
- 知る、感じる、考える
- さまよう若者
- オウムに魅かれた若者たち
カルト問題の行方
オウムに魅かれた若者たち
ある青年の死
今からおよそ5年半ほど前、1994年の夏、27歳の一人の青年が半ば自分の意志でその命を絶った。彼は10代の後半からオカルトに興味を持ち始め、超能力やUFOなど超常現象を専門的に扱った「ムー」という雑誌を愛読していた。昨年12月に刑期を終えて出所したオウム真理教の上祐史浩氏もまた学生時代にこの雑誌を読んでいたといわれている。
彼は20歳前後になると、いわゆる新宗教、あるいは新新宗教に興味を持ち始め、現在カルト教団と呼ばれているようなものにまで関心を寄せるようになる。その中にはオウム真理教の前身である「オウム神仙の会」も含まれていた。四畳半の自分の居室には、所狭しと宗教やオカルト関係の書籍雑誌が置かれており、教育用テープなども散見された。
しかしながら彼は、7~8年の宗教遍歴の末、ついに他界することになる。
その27歳の青年とは、まぎれもない私の実弟である――。
価値観を喪失した時代
現代の若者はなぜオウムのようなカルトに魅かれるのだろうか?
アーナンダと呼ばれた井上嘉浩被告は、初めての公判の中で、出家に至るまでの心境について次のように述べている。
「私は成長するに従って、私のあらゆる側面が自由のきかない管理システムの大きな渦の中で、既にレッテルを貼られ区別され固定され、抵抗するすべもなく自由を失い、絶望の中に沈んでいくのを学生の頃感じました。私たちを取り巻く高度に管理化されたハイテク社会がこのまま暴走を続ければ、私たちの精神は抑圧され荒廃し、近い将来、人類が愛を失い、大規模な破局を自ら引き起こしてしまうのではないかという切迫した危機感を高校生の頃、私は覚えるようになりました。」
すべてのオウム信徒が、社会に対するこのような強い危機意識を持っていたわけではないだろう。なかには大学のサークル気分で入信したものもいるようである。しかし、彼らのほとんどが多かれ少なかれ、自分の人生や社会の在り方、死の意味などについて疑問や不安を抱いていた。
なぜ彼らはそのような疑問や不安を抱かざるをえなかったのであろう?
それは人間として生まれた者の宿命ともいえるが、とくに現代社会にあっては「価値基準の喪失」という問題が大きく起因しているように思われる。
よくいわれることであるが、戦後私たち日本人は「モノ・カネ」に価値の基準を置いてがむしゃらに働き、世界の先進国の仲間入りをした。「貧しさ」や「病い」といったものがまだ私たちの切実な問題だったこの時代、物質的な豊かさが実際に私たちの幸福をある程度保証してくれた。
物質的な豊かさが当たり前となった'70年代後半以降、その価値基準は人々を際限のない欲望充足ゲームに巻き込んでいく。それはやがてバブルの経済として一つのピークを迎えることになるが、その崩壊とともに「モノ・カネ」だけでは人間は幸せになれないのだということにようやく気づくのである。
しかし、一般の人々が物質的な豊かさを謳歌する中で、一部の若者たちは、欲望の充足をひたすら追い求める高度消費社会と、それを支えてきた高度管理社会というシステムに対し、「何かがおかしい」と感じ始める。彼らはおぼろげながらも「欲望」の本質に気づいてしまうのである。
その中の一人が井上被告であり、また私の実弟だったといえるだろう。彼らは社会に対する言い知れぬ不安を感じていたに違いない。そして、その不安からの脱出するべく、新たな価値基準を求めて彼らは「自分探しの旅」に出たのである。
井上被告は麻原という一人の人間の中に「悟り・解脱」という新たな価値基準を見出し、やがてその当初の目的とは正反対の「殺人」いう犯してはならない領域へと足を踏み入れる。我が弟は麻原の中にも絶対的な価値基準を見出すことができず、ついには幻想世界の中で新たな輪廻の旅へ出発する。
どちらの若者も誠に不幸な結末を迎えることになってしまった。
カルトの魅力
彼らをオウムにつき動かしたものは、はたして何だったのだろうか?
その一つは、すでに述べたように価値観の定まらない現代社会への「不安や恐怖からの脱出」であり、もう一つは、彼らにとっての真理である「特定の価値観に基づく自己実現」だと私は考えている。
アメリカの心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求(欲望)というものを次のような五段階に分類している。
- (1)生理的欲求
- (2)安全の欲求
- (3)所属と愛の欲求
- (4)承認の欲求
- (5)自己実現の欲求
これらの欲求は相互に関連しあって生じるものであるが、食欲や睡眠に対する生理的欲求が私たちにとって最も基本的な欲求であり、それが満足すると順次高次な欲求が生じ、やがて自己実現の欲求に辿り着く。
オウムへ入信した若者は、現社会に対する不安や失望から、「安全」な居場所を求めてオウム真理教を選択した。そこでは先輩信者や麻原から「愛情」を受け、修行の進度に比例したステージの上昇によって「承認」されていく。そして、最終的には「悟り・解脱」といった「自己実現」のために明確なゴールが設定されている。
話しを私の弟に戻すが、彼はあるときは、麻原の写真が表紙を飾る『マハヤーナ』という雑誌を見せながら、「空中浮遊をできるらしいんだけど、どう思う?」と語りかけてきたことがある。仏教原理主義者とも言うべき当時の私は、その表紙を一瞥しただけで中身を見ようともせずに、「そんなものは仏教とは関係ないね」と、答えにもならない冷たい言葉を投げ返した。
弟はそれ以上言葉を続けようとはしなかった。なぜなら、その会話の空間には、「安全」も「愛」も「承認」も存在しなかったからである。
ここでは詳しく述べないが、オウム真理教をはじめカルト教団のほとんどが、これら五段階の欲求を充足させる精緻なプログラムを備えているといえる。一度レールに乗ってしまえば、知らず知らずのうちに欲求が満たされていき、自然と心地よさを伴って最終ゴールへ向かうことができるのだ。
既成仏教は無力なのか?
「既成仏教は単なる風景に過ぎなかった」――かつてオウム真理教の信徒が語った有名な言葉である。儀礼中心の葬式仏教、金で買われる戒名・墓地、僧侶の世襲制などなど......、さまざまな批判が既成仏教教団に投げかけられている。
ある席上で私は、オウム真理教被害者弁護団の滝本太郎氏に「既成仏教についてどうのように思いますか。そして何を期待しますか?」と質問したことがある。滝本氏は次のように答えた。
「檀家制度にあぐらをかいたままの既成仏教は、このままでは近い将来滅びてしまうでしょう。オウム問題に対しても門外漢を決め込まず、何か行動を起こしていただきたい......。」
反オウムの立場ある滝本氏が、オウム信徒と同じような思いを既成仏教にい抱いているいるというのは、まことに皮肉なことである。
また、元信徒の永岡辰哉氏は、その著書のなかで「在来宗教がいわゆる一部の若者の問題に対処できなくなっている......」と述べている。ここでいう「在来宗教」とは「既成仏教」のこと、「一部の若者の問題」とは井上被告が抱えていた問題とほぼ同様のもの捉えてよいだろう。
しかし、はたして本当に既成仏教は、オウムの信徒にとって単なる風景に過ぎないのだろうか?
彼らの居場所となることはできないのだろうか?
私は「否」と答える、いや、そう答えたい。
実は、私にもかつて既成仏教が単なる風景に過ぎなかった時期がある。弟の死をはさんで前後5年ほどのことだ。その理由については、必要があれば後日語るこことにするが、当時の私は、宗教を超えた愛と慈悲の現れとしてのボランティア活動に専心していた。
そんな私がなぜ既成仏教に戻ってきたのか――それは現職場、あるいはその周辺に、仏教について真剣に語りあえる仲間がいたからである。サンガがあったからである。セクタリズムを超えて「仏教とは何なのか」、「真理とは何なのか」ということを真剣に話し合う場が、私に大きなきっかけを与えてくれた。
オウムやその他のカルトの問題に関しても、そのような場が今まさに求めらているのだと私は感じている。それぞれがそれぞれの思いを自由にぶつけ合いうことのできる自由な空間――それは私たちが、高度管理社会の中でいつのまにか忘れ去っていたものではあるまいか。オウムに魅かれていった若者たち共に、仏教や真理について語り合える場が今必要とされているのだ。それは役人にも弁護士にもできないこと、唯一仏教者のみができることである。そこから新たな一歩が始まるような気がする。
一人の仏教者として、また肉親を見殺しにしてしまった者として、私自身も大きな責任を感じている。
(大法輪3月号より)