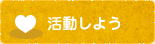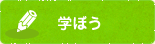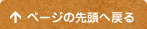- TOP
- 学ぼう
- 知る、感じる、考える
- 子どものこころ
- 虐待・DV
- 0歳のいのちを守れ! "望まない妊娠"をどう支えるか
虐待・DV
0歳のいのちを守れ! "望まない妊娠"をどう支えるか
◆0歳児に忍び寄る危機
もうすぐ、こどもの日がやってきます。お子さんのいるご家庭ではしょうぶ湯に入ったり、鯉のぼりを立てたりすることでしょう。子どもの無事を祈り、健やかな成長を願う気持ちは、昔から変わりません。
しかし、新聞やテレビのニュースに目を向けると、子どもにまつわる話題は決して明るいものばかりではありません。とりわけ多いのが、虐待に関する報道です。実際に、2014年度の児童相談所の虐待相談対応件数を見ると8万8931件と、前年度より実に1万5129件も増加しています。
児童虐待に対する認識が広まったことによって、通報も増えたことでしょう。しかし、到底それだけとは思えない、耳をふさぎたくなるような事例が相次いでいます。
そうした凄惨な虐待事件の陰であまり知られていないことですが、心中以外の虐待死で犠牲になる子どもの約半数が、0歳の赤ちゃんなのです。さらにそのうち0カ月0日つまり産まれたその日にお母さんに殺されてしまう赤ちゃんが、最も多いというのです。
最近では、東京都心のオフィスタワーに入った歯科医院のトイレに、女の赤ちゃんが産み落とされたまま放置されていたことが大きく報道されました。この4月にも、福井県の下水処理場でへその緒がついたままの赤ちゃんの遺体が見つかりましたし、岐阜県でも、袋に入れられた赤ちゃんの遺体が病院の前で発見されています。
また1月には、静岡県で18歳の女子高校生が、交際相手の男子高校生とともに産んだばかりの赤ちゃんを窒息させて殺害するという事件も起きました。互いの両親も周囲の人も誰も妊娠に気づくことなく、本人たちも誰にも相談しないまま、出産の日を迎えてしまったのです。
どの事件に対しても、インターネット上には当然のことながら身勝手さと無責任さを責める声があふれました。しかし静岡県のケースでは、出産直後、2人がどこか相談できる機関がないかとスマートフォンで検索していた形跡があると、捜査関係者は述べています。
出産時期になるまで誰にも妊娠を打ち明けられず、最悪の行動に出てしまった2人――あまりにも稚拙ですが、身近な誰かに妊娠の事実を打ち明けてくれてさえいたら、あるいは適切な機関にうまくつながることができていたらと、悔しい思いがしてきます。
◆足りていない相談窓口
赤ちゃんを産んですぐに死なせてしまったお母さんは、そのほとんどが「望まない妊娠」だったことを告白しています。
以前より周産期医療の現場では、子どもへの虐待を行った母親が妊娠期に妊婦検診を受けていなかったり、母子健康手帳の交付を受けていなかったりする割合が多いことが知られていした。出産後すぐに子どもを遺棄したり放置したりした母親の場合には、そのほとんどが未受診・未交付であるといった状態です。
これまで、虐待防止といえば出産後に行う対策が中心でしたが、虐待リスクの高い母親やその家族に対しては、妊産婦の時期からより有効な対応を行うべきだという声が近年、高まってきました。
望まない妊娠をして戦々恐々と日々を過ごしている彼女らにとっては、匿名が守られ、安全が感じられるような身近で相談しやすい窓口が増えることが必要なのです。
事情があって育てられない赤ちゃんを保護している、通称〝赤ちゃんポスト〞で有名な熊本県の慈恵病院では、子どもを預ける前に、秘密は守るのでぜひ一度相談してほしいと呼びかけています。
慈恵病院が運営する24時間対応の匿名の妊娠相談窓口には、電話やメールで年間数千件もの相談が寄せられていますが、地元である熊本県内からの相談はわずかで、そのほとんどが他地域からのものだといいます。
「まだ学生なのに妊娠してしまった」「妊娠を伝えたら彼と連絡が取れなくなった」など、切羽詰まった妊娠相談の需要に対して、身近な窓口が足りていないことの現れなのかもしれません。
こうした状況を打開しようと、たとえば大阪府では2011年、全国で初めての都道府県レベルでの妊娠相談窓口「にんしんSOS」を開設しました。ここでは保健師や助産師が、電話は平日の日中に、メールでは24時間体制で対応にあたっています。「にんしんSOS」でも、当初は府外からの相談がかなり多かったということですが、同じような取り組みが全国に波及して、今では自治体運営の相談窓口が30カ所ほどにも増えたということですから、今後はより地域に特化した情報の提供が期待されます。しかし、専門家からは「まだまだ相談窓口が足りない」という声が上がっているのが実情です。
◆あまり知られていない「特別養子縁組」
望まない妊娠をしたまま臨月を迎える女性たちの多くは、貧困や性的虐待、DV、レイプ被害など、人には知られたくない深刻な事情を抱えています。そんな「産みたいけど育てられない」「産むしかないけど育てられない」という女性とお腹の赤ちゃんにとって福音と言えるような取り組みが、「特別養子縁組」という方法です。
特別養子縁組は、いわゆる一般的な養子制度とは異なるものです。子どもの利益のための制度として、1988年に施行されました。対象となるのは、原則として6歳までの子どもたちです。
産みの親に事情があって育てられないという場合に、産みの親には親権が残ることなく、育ての親の戸籍に実子と同じように入ることのできる制度です。育ての親の元で、子どもに恒久的な家庭を与えることを目的としています。日本では現在、適切な保護者をもたない乳幼児は、その80%以上が施設に預けられています。それぞれの現場では職員が懸命に世話をしていますが、複数の子どもを同時に養育しなくてはならない施設で、家庭とまったく同じような養育環境を求めるのは不可能なことでしょう。
もし、ぜひ子どもを育てたいと望む家庭があって、そこで乳児の頃から一対一の愛着を結ぶことができるならば、子どもにとってこれ以上の安心はありません。しかし、日本では血縁へのこだわりが強いせいか、特別養子縁組を受けることのできる子どもはほんのわずかであるのが現状です。
◆赤ちゃんとお母さん主体の支援を
ここに、多くの自治体のモデルとなっている、通称「愛知方式」と呼ばれる特別養子縁組の取り組みがあります。これは、これまで里親さん主体の制度だったものを、赤ちゃん主体の制度として位置づけたところに大きな特徴があります。
たとえば、愛知方式では次のような条件を里親さんに受け入れてもらってはじめて縁組が進みます。一部、内容をご紹介いたしましょう。(参考:『「赤ちゃん縁組」で虐待死をなくす――愛知方がつないだ命』光文社新書)
◎妊娠中の母体保護と胎児の安定に協力し、このことを妊婦さんへ告げて安心させてあげることに積極的に賛同します
◎家庭裁判所による養子縁組成立の審判以前に、産みの親から子どもを引き取りたいという申し出があった場合には、児童福祉専門職者の意見を参考とし、子どもの幸せを願ってどのようにつらくても育てた子をお返しいたします
◎子どもの性別を選びはせず、妊娠経過についてどのような事情があろうとも一切不問として育てます
◎分娩後の赤ちゃんの障害の有無で家庭引取りを左右したり、養子縁組許可申立を取り止めたりするようなことはいたしません
◎産まれた赤ちゃんに重度の障害があったり、未熟児分娩であったりしたため引き続き入院継続を要し、将来にわたっても専門施設等での療育が必要とされる場合でも、私たちがこの子の親となる決断をしたことを変える考えはありません
◎養子に迎えたわが子には、産みの親と別れた経緯を知る権利があることを理解し、将来、適切な時期を選んで産みの親を傷つけないことに配慮しつつ、真実告知いたします。
いかがでしょうか。厳しい、とお感じになった方も多いかもしれません。その通りで、こうした説明をすると、それでも養育したいというご家族はごくわずかとなってしまうそうです。それでも、大切な子どもの人生がかかっているのですから、当然、納得していただくべきなのかもしれません。
また、この愛知方式が特徴的なのは、事情があってどうしても子どもを手放さなければならないというお母さんを、養育希望者が一緒にサポートすることです。
望まない妊娠をして悩み、苦しみ抜いてきた産みのお母さんは、ほとんどの人が重い罪悪感に苛まれています。人目を避け続け、状況によっては自殺を考えるほどに追い詰められているのです。
愛知方式では、産みの親と養育希望者をうまくマッチングできそうだと判断された場合には、専門家を仲立ちとしながら両者を積極的に会わせています。待望の赤ちゃんが迎えられることを心底喜んでくれる養育希望者を目の当たりにして、産みのお母さんは心の底から安堵し、涙を流す人も多いそうです。
望まない妊娠をした女性を責めるだけでは、誰も幸せになりません。本当は、複雑な事情を抱えてこうした状況に至ってしまったお母さんにこそ、心身ともに手厚いケアが必要なのです。愛知方式のような方法がもっと世間に認知されて、幸せな赤ちゃんとお母さんが増えることが望まれます。
◆いのちに関する価値観を議論しよう
女性と男性、この両性がなければ子どもの誕生はありえません。しかし、これまでの事例を見ていただいてわかるように、当事者である男性の影は極めて薄いのが現状です。天より産む性を仰せつかった女性にしか味わえない喜びがある反面、女性だからこそ背負わねばならない苦しみがあることを、改めて実感します。
この非対称性は避けられませんが、だからこそ子どもたちには早い段階から、偏りのない、本当に幸せに赤ちゃんを迎えることができるための教育をすることが求められます。
また、いのちについての価値観が多様化しているにもかかわらず、それらに関する議論が深まっていかないことも懸念されます。平均初婚年齢の上昇により不妊治療をするカップルが急増するなか、この国の人口妊娠中絶の件数は年間20万件というすさまじさです。
子どもを持つ、持たないという権利を、先進諸国と言われる国々の女性が勝ち取ったのは実はごく最近のことで、それ自体を否定するつもりはありません。しかし、妊娠してしまっても中絶すればいいという安易な思考に世の中が偏っていかないか、心配でもあります。
出産前に子どもの障がいの有無を調べる出生前診断も、安易な中絶につながるという批判の声をよそに、既に一般的な検査として導入が始まっています。生まれてこようとしているいのちを私たち一人ひとりがどうとらえるのかを、仏教者こそが真剣に考え、指針を示していかなければ、生殖医療の目覚しい発達のなかで大切なことを置き去りにしてしまうことにもなりかねません。
お寺の未来を案ずる前に、いのちに関する議論に、仏教者はとりわけ敏感であってほしいと願っています。(吉)