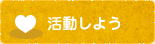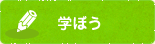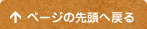- TOP
- 学ぼう
- 知る、感じる、考える
- 仏教と社会
- エンゲイジド・ブッディズム入門ーティック・ナット・ハンの教えからー
社会とかかわる仏教
エンゲイジド・ブッディズム入門ーティック・ナット・ハンの教えからー
神 仁
エンゲイジド・ブッディズム〝E n g a g e dBuddhism〞という言葉をお聞きになった方はどのくらいいらっしゃるでしょうか? 社会活動をする仏教者の中では、少しずつ定着しつつある言葉ではありますが、その日本語訳や定義についてはいまだ不確かなままと言えるでしょう。訳語に関してみただけでも、「社会参加する仏教」「社会を作る仏教」「社会とかかわる仏教」「行動する仏教」「闘う仏教」など、まさに多岐にわたっていることが、その実情を表しています。
私はイラク攻撃が始まった2004年に、仲間と共にエンゲイジド・ブッディズムについての研究会を立ち上げ、4年にわたってさまざまな情報をもとに考察を重ねてきました。その中から、ここではまず、エンゲイジド・ブッディズムという言葉を最初に使ったベトナム人僧侶、ティック・ナット・ハン(Thich Nath Hanh)の思想と活動をもとに、エンゲイジド・ブッディズムとは何かについて考えてみたいと思います。
◆柔らかな風
今から15年ほど前のことでしょうか、著述業を営む友人に誘われて、東京で開催されたナット・ハン師の講演会に出席したことがあります。会場には20代から40代の人を中心に、500人ほどの聴衆がつめかけ、ごった返していました。
舞台袖から静かに登場したナット・ハン師は、小柄でもの静かな雰囲気の、柔らかな風のような人のように見受けられました。高名な僧侶といえば、きらきら、あるいはぎらぎらとしたオーラが漂い、威風堂々としたイメージをつい思い浮かべてしまうところですが、ナット・ハン師から受けた印象はそれとはまったく異なるものでした。
聴衆の中には僧侶も混じってはいましたが、その多くが一般のフリークの人たちだったように記憶しています。それがために私は、当時の流行になっていたニューエイジ・ブームを担う活動家の一人のように師のことを受け止めてもいました。
講演は終始おだやかな雰囲気の中で行われ、会場全体がまさに柔らかな風に包まれたようでした。その風のゆりかごの中で私は知らずと眠りに落ちてしまったことを告白しておきます。これまでの人生の中でただ一度のご縁であり、今思えばまことに残念なことをしたとも言えるのですが、それは師が持つ、ゆりかごのように誰もを包み込んでしまう温かく柔らかな力のゆえんであったと思うのです。
◆アンガジュマン
ナット・ハン師は、1926年にベトナムの中部で生まれ、16歳で仏門に入り僧院で生活をします。しかし、当時の僧院生活や修行のあり方に疑問を感じて、「僧侶も科学や西欧思想を学ぶべきだ」と主張し、僧院を追われたこともありました。
ベトナムは大乗仏教と上座部仏教が共に流入し信奉されてきた思想的・宗教的に自由な国です。そのような伝統的な土壌に加え、フランスの植民地化にあって、西欧思想が流入していたことが、ナット・ハン師に少なからず影響を与えていたことは、想像にかたくありません。
フランス語のアンガジュマン(Eengagement)は、フランスの実存主義の中でサルトル(JeanPaul Sartre)などが用いた「参加」を意味する言葉であり、ラテン語では船の「錨(いかり)」を意味しています。サルトル自身は晩年マルクス主義に傾倒していきますが、「人間は自らに責任を負う存在として根本的に自由である」「自己を選ぶということは同時に世界を選ぶことであり、世界全体に責任を負うことである」などと、実存主義について解説をしました。
サルトルはこのアンガジュマンという言葉によって、人びとに対して宿命論や運命論に囚われるのではなく、政治参加することをうながしたのです。
1960年代、ナット・ハン師は、激化するベトナム戦争の中で犠牲となっていく多くの人びとを目の前にしながら、自己のさとりのみを追求する僧院生活に大きな疑問を感じるようになります。やがて、戦争の犠牲となって社会苦にあえぐ人びとの支援活動に従事することとなるのでした。
僧院を出て、社会苦にあえぐ人びとを救うこと、その活動を精神的に後押ししたのは、師匠であったテック・クアン・デュクであったと考えられます。クアン・デュク師は1963年に、ゴ・ジンジュム政権下での戦闘の激化や仏教弾圧に対して、政権を後押ししていたアメリカの大使館前で、焼身供養をもって政策の転換を促した人です。
その後30人にも及ぶ僧侶がクアン・デュック師に続いて焼身供養をとげ、結果としてアメリカ政府にも少なからず影響を与えることになりました。もちろん愛弟子のナット・ハン師にとってはなおさらのことであったに違いありません。
◆戒・定・慧の三学
これまであまり強調されてきませんでしたが、私は、ナット・ハン師が行ってきた慈悲行としての社会活動の原点には、古来、仏教で説かれてきた戒・定・慧の三学があると受け止めています。師は自らが創設したティエプ・ヒエン(相互生存)教団において、14の戒を定めました。そして、この戒の中で、師は定と慧の重要性について明確に触れています。
代表的な著書『ビーイング・ピース〝BeingPeace〞』からご紹介しましょう。
「戸惑いの中で、(移り変わる)環境の中で、自己を見失ってはいけない。身心の落ち着きを取り戻し、こころの集中を行い(念)、こころの統一を促進し(定)、洞察を深めること(慧)を修しなさい」(拙訳、カッコ内筆者補足。以下同。)
これは、14の戒の7番目の戒で、最も中心とすべき戒だとされています。とくに、今日の日本の仏教ではあまり重要視されていませんが、師がことさらに強調するのが「念」(パーリ語:Sati、英語:Mindfulness)です。すなわち、仏教の修養徳目として重視される「八正道」の中で説かれるところの「正念」でもあります。それは、自己の内も外の世界も正しくとらえ、観じていくことであり、東南アジアをはじめとする南方の仏教国では、今でも特に重んじられています。ここでは深くは触れませんが、その背景には、近年日本でも徐々に浸透してきている「ヴィパッサナ」という瞑想法(観法)の影響が強くあるように思われます。
◆社会苦にかかわる
また、第9戒では社会参加についての言葉が次のように述べられています。「常に真実にしたがって建設的に話しなさい。たとえ自身の安全が脅かされる可能性があったとしても、不正義について声を大にして語る勇気を持ちなさい」
元をただせば、お釈迦さま自身も、戦争によって引き起こされる社会苦に対して積極的な発言をしていますから、ナット・ハン師の言葉もお釈迦さまの教えに基づいたものだといえるでしょう。
しかし、政治との関係については、一線を画すべきだとして、10番目の戒で次のように定めています。「仏教の共同体を個人の利益のために用いたり、自分たちの共同体を政治的な党派に変えてはならない。しかしながら、宗教団体は抑圧と不正義に抗する明確な立場をとるべきである。抵抗運動に加担することなく、状況を変えることに専心するべきである」
アメリカにおいて出版されたエンゲイジド・ブッディズムに関する書籍の中で、日本のエンゲイジド・ブッディズムの代表として、政治に積極的にかかわろうとしている新宗教団体の名前が挙げられています。しかしながら、本来のエンゲイジド・ブッディズムの原意を顧みれば、このような認識は的を射たものではないことがわかってきます。
今日、社会活動に参加する仏教者の中でも、この点に大きな誤解が生じているといえるでしょう。ときおり、エンゲイジド・ブッディズムの名の下に、仏教者を中心とした政治団体を作るべきだとの話を耳にすることもありますが、このようなことは、ナット・ハン師の思いとはかけ離れたものと言えます。この10番目の戒は、宗教団体と政治の関係性、僧侶と政治の関係性について大きな示唆を与えています。
◆自己の開発と社会の開発
冒頭で申し上げたように、今日、エンゲイジド・ブッディズムという言葉は、少しずつ日本の仏教界に浸透しつつあります。しかしながら、その理解や定義については、「社会参加」としての側面ばかりが強調されているような気がしてなりません。それは、社会参加をせずにひきこもり傾向にあると指摘される日本の仏教、僧侶や寺院を刺激するためには、ひとつの方便として有用なことでしょう。
しかしながら、社会参加はエンゲイジド・ブッディズムの一側面であり、包括的な理解の仕方とは言えません。ブッディズムという言葉を使っている以上、社会苦に取り組んでいる一般の社会事業や平和運動とは区別されるべきものであり、その際の根拠は何かということになってきます。
それは、自己の本質とつながり、社会とつながっていくこと、自己の内面的な開発と社会の開発を同時に行っていくことが、エンゲイジド・ブッディズムの本義であろうと、私は考えています。
その意味で、あえて誤解を恐れずに浄土教の言葉を借りて表現するならば、「往相回向と還相回向」が同時になされること、それがエンゲイジド・ブッディズムのありようだとも捉えることができるのです。
そのようにみてみると、エンゲイジド・ブッディズムは大乗仏教本来のあり方とまったく矛盾しないことにも気づくのです。自らの救いと他者の救いを同時に追求していくことが両者においては重要視されます。エンゲイジド・ブッディズムは、現代社会における大乗仏教のリノベイションと言うこともできるのではないでしょうか。
さて、そこで課題となるのが、ナット・ハン師らが重きを置いている戒・定・慧について、日本の仏教界がどのような理解を今後していくかということです。戒・定・慧の三学を軽視する向きのある日本仏教の中で、エンゲイジド・ブッディズムを真の意味で定着させるためには、原点回帰をするか、もしくはそこに新たな解釈を付け加えていかねばならないことになります。
繰り返しになりますが、仏教者が社会参加をしさえすれば、それがそのままエンゲイジド・ブッディズムであると考えることは、いささか飛躍したとらえ方だと言えるでしょう。この課題をどのようにクリアしていくのかが、いま問われているのです。
さて、エンゲイジド・ブッディズムが「社会参加する仏教」「社会を作る仏教」などと訳されるとき、その原語と考えられるのは、ナット・ハン師が言ったエンゲイジド・ブッディズムではなく、むしろ、ソーシャリー・エンゲイジド・ブッディズム〝Socially Engaged Buddhism〞という言葉ではないかと私は考えています。
この言葉を最初に使ったのは、タイの仏教者であり社会活動家であるスラック・シバラクシャ(Sulak Sivaraksa)氏であったことを付け加えておきます。