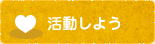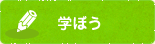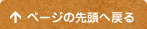- TOP
- 学ぼう
- 知る、感じる、考える
- 仏教と社会
- いのちの現場に飛び込む―仏教者によるターミナルケアー
社会とかかわる仏教
いのちの現場に飛び込む―仏教者によるターミナルケアー
ぴっぱら2008年11月号掲載
すべての人は平等に、いつか必ず死にゆく運命です。この世に人間の苦しみは数多く存在しますが、なかでも愛別離苦、つまり親や配偶者、友人など、愛する人や大切な人と別れなければならないという苦痛は、はかりしれないものです。
高齢化社会を迎えているわが国においては、「ターミナルケア」の必要性がにわかにクローズアップされています。み仏の教えをもって、死を迎えようとしている人、また、残される家族のこころに添い、恐れを取り除くことは、まさに仏教者に与えられた役割であるといえるでしょう。
仏教者は、古くから葬儀や法要という宗教的儀礼を通じてその菩提を弔い、残された遺族のこころを慰める役割を担ってきました。しかし、お寺や僧侶の存在意義が問われる昨今、さらにその役割を見つめなおし、地域のため、広く人びとのために活動しようというさまざまな試みも行われています。
中下大樹さんは浄土真宗大谷派の僧侶として、仏教によるターミナルケアを行う新潟県の病院に勤務し、末期状態にある患者のこころのケアを行ってきました。そして、その経験をもとに、現在では僧侶の社会貢献活動のための寺院ネットワークの立ち上げにも力を注いでいます。中下さんが終末期医療の現場で感じたことは、どのようなものであったのでしょうか。
◆忘れられない光景
先日、懐かしい名前が書かれた暑中見舞いを受け取った。私は、数年前まで仏教系のホスピス(緩和ケア病棟)で、末期癌患者さんの看取りに従事していた。そこでご縁があった遺族Aさんからの暑中見舞いである。ホスピスを退職しても、ときどき手紙や電話を遺族からいただくことがある。Aさんは、ひとり娘をホスピスで看取っていた。
病名は舌癌。Aさんの暑中見舞いの文面を読み進めるにつれて、「私は生まれ変わったら、学校の先生になって、生徒にいのちの大切さを伝えたいな」と、哀しい目をして最後に筆談で私に語ってくれた亡き娘さんの姿が思い出された。そして、忘れられないあの光景が徐々に私の脳裏に蘇ってきた。
火葬場の職員までもが涙ぐんでいた。その場にいた誰もがこみ上げてくるものを我慢できなかった。まだ10代の我が子を喪った母親は半狂乱になり、「いやだー、娘はまだ死んでいない!これは嘘よー、夢よ!」と釜の前で泣き叫び、棺にすがりついた。それは、これからまさに棺が釜に入れられようとする瞬間であった。
「私の娘に触らないで!」と、ものすごい目つきで睨み返す母親に対して、その場にいた誰もが何も言えず、ただ愕然と立ち尽くしていた。
それからどのくらいの時間が流れただろうか。心身ともに疲れ果てた母親が、膝から崩れ落ちるように、その場に倒れこんだ。急いで皆が駆け寄る。白目をむいて気絶した母親は、親族の車に乗せられ、病院へと運ばれた。
その後、火葬場の控え室へ向かう人たちは皆一様に無言であった。誰もが、若すぎる理不尽な「死」に対して、やり場のない怒りのようなものを感じていた。「人生とは不公平だね。代われるものなら私が代わってあげたいよ。なんで......、なんで......」お孫さんの将来を楽しみにしていたであろう、祖父とおぼしき男性が呟いたその言葉が、今でも耳から離れない。
その後数か月が過ぎ、ホスピス内にある仏堂で、その年に亡くなられた方を偲ぶ新盆の追悼法要(遺族会)が行われた。もちろん、そこにはAさんの姿もあった。法要が終わると、その後の茶話会にてAさんが私に話しかけてきた。
「毎日暑いですね?元気にしていますか?」
「はい、おかげさまでなんとかやっております。Aさんはいかがですか?」
「ええ、何とか。でも、娘と同じ歳くらいの女の子を見ると、やっぱり辛くて」
「......」
「中下さん、娘の死を忘れないでね。娘の分まで、あなたが精一杯生きてあげて。そして、人の痛みの分かる立派なお坊さんになってくださいね。それが娘の供養になるから。いのちを粗末にしないでね。頼んだわよ」
Aさんの声は涙ぐんでいた。しかし、力強い声だった。いただいたいのちと人生を精一杯生き抜いてほしいという「願い」を強く感じた。まさに、「いのち」のバトンタッチが行われた瞬間であったように思う。
◆生きることは願うこと
人は誰かの「願い」によって、自分が「生かされている」と感じた時、生きる力が湧いてくるのだと思う。「人の痛みの分かるお坊さんになってほしい」と私に「願い」をかけてくれたAさんの言葉は、僧侶として生きる私の原点となった。今でも僧侶としての生き方に疑問を持つと、必ずその言葉を思い出し、原点に立ち返るようにしている。
そして、「今まで自分は何を願って生きてきたのか、これから何を願って生きていくのか」ということを絶えず自問自答しながら、自分がこの世から去ってしまった後も、残された誰かが私の志を引き継ぎ、誰かがその願いの実現に向けて歩き出そうとする姿を少しだけ想像してみる。すると、生きることがなんだか楽しくなってくる。生きること、それは「願う」ことだと私は感じている。
人の生き方は死に方にも通じていて、生きてきたように人は死んでいくというのが私の持論である。どの死に方が良くて、どの死に方が悪いとか、こちらが決めるのはおこがましいとさえ思う。
「如実知見」という言葉があるように、まずありのままの姿を見て、どれだけこちらが、自分と異なる他者をも受け入れようとする気持ちがあるかどうか、そのことが問われている気がするのだ。
実際問題として、ホスピスで亡くなる患者さんのすべてが、穏やかで安らかな死を迎えるとは限らない。誰にも看取られることなく、ひとり孤独に亡くなられる方も実際にはかなり多い。「ありがとう」という感謝の気持ちを持って、安らかな笑顔で亡くなられるというケースは、残念ながらごく稀である。
家族(遺族)の反応もさまざまである。長い間、いろいろと家族間に問題があった場合、家族の一人がホスピスに入院したからといって、いきなり家族関係が修復し、良くなるというようなケースはほぼ皆無と言ってよい。
また、宗教というものに普段から馴染みのない方にとって、入院した病棟内に宗教者(僧侶)がいるというのは、必ずしも望ましいことではない。「縁起でもない」「まだ私は死んでいない」と、僧侶の私は入院患者さんから散々言われ続け、精神安定剤を飲みながら病棟に向かっていた時期もある。
しかし、心をこめて、ひとりの人間として患者さんや家族に寄り添おうと心に決めてから、次第に心を開いてくれる患者さんや家族が増え、受け入れてもらえるようになっていったと思う。Aさんもその一人であった。
◆僧侶の役割とは
私たち僧侶は、自らを「死」の専門家であると考えているのではないかと感じる時がある。確かに、死後の仏教儀式を司る専門家ではある。しかし、なぜ僧侶という存在が病院内では「縁起でもない」と言われ、僧衣を着て正々堂々と病院内に入ることが出来ないのだろうか?
「いのち」の大切さを説く私たち僧侶が、病院という「いのち」の現場で、医療従事者からも快く思われていない理由を真剣に自問自答してみる必要があるだろう。
救いを求める患者さんや家族は現に、私たちのまわりには大勢存在するのだ。「いのち」を説く前に、「いのち」の現場にまず飛び込むことが、今ほど求められている時代はない。
首都圏では、葬儀や法事そのものをしないというケースが確実に増えつつある。経済的な理由で葬儀ができないという人が増えていると同時に、あえて宗教者を呼ばないという人、病院から火葬場へ直行する、いわゆる火葬のみ( 直葬)の件数も確実に増えてきているという。このような傾向は今後ますます顕著になっていくことだろう。
少子高齢化、核家族化、離婚や非婚の増加など、社会構造は大きく変化し続けている。後継ぎがいないお墓は、今後増えてく一方で、減ることはない。また、過疎地からはお寺そのものが消滅していく可能性もある。お寺を巡る状況は前途多難であると、現段階では言わざるを得ない。
葬儀や法事は言うまでもなく、僧侶にとって大事な布教の場でもある。しかし、葬儀や法事すら満足にできなくなった時に、私たち仏教者は一体どこへ向かえばよいのだろうか?
僧侶として何ができるかを考える前に、人間としてこれからの時代をどう生きていきたいのかが問われている気がしている。
◆できることをできる範囲で
「いのちには限りがあるのですよ。だからこそ、限りあるいのちをあなたはどう生きたいのですか?何を拠り所として、これから生きていくのですか?」亡くなっていかれた患者さんをはじめ、先立った人は皆、私に問い与えてくれた。皆、導師であった。
「人間の死亡率は100%」という言葉がある。人はいつか死ぬ。ならば、与えられた寿命を全うすること、いつお迎えが来ても悔いがないような生き方をすること。それが、今の私にできるAさんへの精一杯の恩返しであると思っている。
「娘が大好きだった向日葵です」と、葉書の最後には向日葵の絵が描かれてあった。
Aさんへの暑中見舞いの返事を書きながら、柩いっぱいに埋め尽くされた向日葵の中で静かに微笑む、Aさんの娘さんの優しい顔を私は思い出した。
「あなたの死を決して無駄にはしませんよ。仏教者として、できることをできる範囲で、精一杯やっていきますから、見守っていてください」と私は心の中で誓い、Aさんへの返信葉書をポストに投函した。