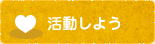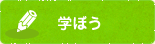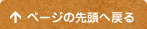- TOP
- 学ぼう
- 知る、感じる、考える
- 仏教と社会
- 宗教者による被災者のグリーフ(悲嘆)ケアのあり方について
社会とかかわる仏教
宗教者による被災者のグリーフ(悲嘆)ケアのあり方について
ボランティア・デビュー
平成二十四年三月十一日----
雪模様という前日からの天気予報とは異なり、被災地最多の死者・行方不明者を数えた石巻の地は、おだやかな春の日差しが降り注ぐ好天に恵まれた。牡鹿半島の付け根にある寺院で、その日の午後に催される一周忌法要に参列する予定であった私は、午前中にどうしても訪れたい場所があった。
それは、児童・教職員七十九名が亡くなり、未だ五名が行方不明のままの石巻市立大川小学校である。
臨時に作られた慰霊用の祭壇の前には、花や線香を手にした方々が次々と訪れ手を合わせていた。その中に、四~五歳とおぼしき男の子を連れた一人の母親の姿があった。若い母親は祭壇の前でうずくまり「○○ちゃん、会いに来たよ」と言いながら嗚咽を漏らした。その母親の背中を慰めるように両手でさする幼い男の子の姿が、けなげであり不憫にも思われ、私の胸を詰まらせた。
ご遺族の悲嘆(グリーフ)が癒されるまでにはまだまだ時間がかかる----そのように、あらためて思われた瞬間だった。我が子を失った親の悲嘆は、察するに余りある。本人の苦しみや辛さをそのままに代わって感じることは出来ない。しかし、生と死の世界をつなぐ宗教者として、ご遺族のこころを癒すはたらきをすることは使命とも言える。
昨年の三月十一日以降、私は、岩手、宮城、福島三県を何度となく巡り歩いた。震災直後の支援活動は、不足物資の配給と炊き出しが主なものだった。五月に入ってからは、避難所での映画上映、コンサート、子ども会なども行うようになった。やがて夏を迎える頃には、心身のケアを考慮してハーブティー・サロンを仮設住宅で開設した。
その間、合間合間にお亡くなりになった方々の仮埋葬の場などに立ち会い経をあげた。経をあげていると御身内の方以外にも、どこからともなく人が集まって来て、そっと一緒に手を合わせてくれた。お経と祈りの力を今さらながらしみじみと感じさせられた。
震災からほどない頃、避難所を周りながらよく聞いた言葉がある。それは、「あのとき私も一緒に流されていれば......」というものだった。その言葉は、被災者のほとんどが、仮設住宅や借り上げ住宅に移り住んだ今でも、とくに高齢者の方々からしばしば聞かれるものでもある。
内閣府および警察庁は、三月九日、震災関連の自死者が五十五人に上ると発表した。この数を多いと捉えるか少ないと捉えかは、人によって判断が分かれるところであろう。しかし、阪神淡路大震災後に自死を含む関連死でお亡くなりになった方の数が、五年経過時点でおよそ九百五十名にも上り、二年、三年と経過していくにつれて増加していったことを、あらためて記憶に留めておく必要があろう。今回の震災規模から察するに、適切な対応がなされない場合には、自死を含めて三千名もの「生き残ったいのち」が失われる可能性があるということになる。
「生き残ったいのちをこれ以上ひとつも失うことのないように」という願いが、震災当初から私の行動の源になっている。その上で、あの日から一年が経ち、今もっとも宗教者に問われているのが、被災した方々の悲嘆感情に対するケア、すなわち「グリーフケア」でなないかと考えている。
グリーフとは、人が愛し依存する対象を失ったとき(喪失体験)に生ずる「悲嘆の感情」をさす。精神分析学者のフロイトは、愛する人を失うことで生じた悲嘆の現実と向き合い、その悲しみを受け入れて新しい生き方に気づき、再出発するまでの必要な作業をグリーフワークと名付け、これが、こころを癒すための重要なプロセスだと指摘している。このグリーフワークを第三者が支援することが「グリーフケア」である。
だれしもが家族や親しい人を亡くせば、悲しく辛いグリーフを体験するもので、これ自体は正常な反応であり、ごく当然な人間の感性でもある。しかし、その感情が癒されることなく継続する場合、やがて心身の病気を引き起こしてしまうことがある。災害時の場合にはとくにPTSDなどの発症が懸念される。
その意味では、何らかの喪失体験をした初期段階で、第三者、とくに宗教者が関与する適切なグリーフケアが求められている。
上智大学グリーフケア研究所の髙木慶子氏は、主な喪失体験について次のようなものを挙げている。
- 愛する家族や親戚、友人などを喪失=死別、離別(失恋、裏切り、失踪)
- 身体的喪失=病気による衰退や身体の一部の喪失(子宮・乳房・頭髪など)事故による負傷
- 所有物の喪失=財産、住居、仕事(リストラ)、ペットを失うなど
- 環境の喪失=転勤、転居、転校などによる親しみなれた地域社会や故郷などとの別れ
- 役割の喪失=地位、役割(家庭内での役割、子どもの自立。定年など)
- 自尊心の喪失=仕事の失敗からくる名誉・名声のはく奪。災害時、避難所などでプライバシーが守れない。悪口、うわさ話。
- 社会生活の安心と安全の喪失
今回の震災においては、原発事故による避難者を含めて、未だ三十四万人もの方々が避難生活を送っており、そのほとんどの方が何らかの形でこれらの喪失体験を経験していることになる。地震や津波で家族を失い、家も流され、仕事も失ったという、複合的な喪失体験をされた方々もけっして少なくない。
特に男性の場合は、仕事や社会的地位がアイデンティティー(自我同一性)の拠りどころになっている場合が多いため、たとえ家族がみな無事だったとしても、その喪失感は深く、癒すことがはなはだ困難なケースがある。ときには、「孤立→アルコール依存→うつ→自死」というプロセスをたどる場合もあることは、阪神淡路大震災後の経験からも指摘されているところである。
実際に仮設住宅を回って、ハーブティー・サロンを開設しながら傾聴活動を行っていると、孤立している高齢男性が多いことに気づかされる。住宅からまったく出て来ない方、ようやく出ては来ても人の輪に入れず、一人、集会所の片隅で静かにお茶を飲む方など......。
そのような方にこちらから声をかけると「俺は一人でいいんだ」「あいつらは別の集落の人間だから」などと、ほぼ、あきらめにも似た答えが返ってくる。しかし、そのこころの内には、深い孤立感や孤独感が横たわっているように思われる。PTSDばかりではなく、うつ病の発症を防止するためにも、きめ細かなグリーフケアがいま望まれている。
悲嘆からの回復へ至るプロセスについて、アルフォンス・ディーケン氏は、次のような十二段階があると説明している。
- 精神的打撃と麻痺状態
- 否認
- パニック
- 怒りと不当感
- 敵意と恨み(ルサンチマン)
- 罪意識
- 空想形成・幻想
- 孤独と抑うつ
- 精神的混乱と無関心(アパシー)
- あきらめ----受容
- 新しい希望----ユーモアと笑いの再発見
- 立ち直りの段階----新しいアイデンティティーの誕生
悲嘆感情は、必ずしもこれらの十二段階を順序よくたどって癒されていくわけではないが、グリーフケアに携わる者は、基本的な知識として押さえておいた方がよい事柄である。
昨年の十二月末に、ある避難所の集会所でクリスマス会を催していたところ、いきなりドアを開けて「何でクリスマス会なんかやるんだ! おまえら坊主だろ!」と怒鳴り込んできた中年男性がいた。震災で多数のいのちが失われているにもかかわらず、クリスマス会など浮かれたことをやるんじゃない。ましてや僧侶がクリスマスなどとんでもない、という意思表示であったように表面上は受け止められる。
しかし、彼の行動は十二段階のプロセスにおける「怒りと不当感」「敵意と恨み」という感情の表出だったと理解することができよう。また、「孤独と抑うつ」状態にあるがゆえの反射的な行動だったとも捉えることができる。もし、回復のプロセスへの知識がなく、彼の怒りに対して怒りをもって対応したならば、本人のグリーフの度合いはより深刻なものになっていった可能性がある。
このときは、スタッフとして参加していた一人の僧侶が、彼の感情を否定したり非難したりせず、集会所の奥に招き入れ、お茶をのみながら膝と膝をあわせてその思いをじっくりと聴いた。ほどなくして彼の怒りに満ちた表情は柔らかくなり、冷静に言葉を交わすことができるようになっていった。
さて、そのように考えてみるとき、いま宗教者に求められているのは、グリーフからの回復までの、マラソンの伴走者になることではないかと考えている。被災者の方にそっと寄り添いその気持を受け止め、必要なときには声をかけながら、ご本人が回復というゴールテープを切るまで伴走していく。
途中、怒りや悲しみを表出したときには、野球のキャッチャーのようになってその感情を受け止める。そのような姿勢とこころの有り様が支援する側に求められている。
また、今回の震災で宗教者が担うべきは、「死者と生者をつなぐグリーフケア」ではないかとも感じている。
物資の配給や炊き出し、こころを癒すアトラクションやコミュニティー作りなどは、行政や一般のNPOも行っていることであり、宗教者よりもノウハウやスキル、ネットワークをもっている場合が多い。とくに、被災直後の復旧活動や被災者の心身のケアは、自立完結型の自衛隊や、専門のスキルと経験を持った医師・看護師に委ねざるを得ない。
私はこれまでにもさまざまな場所で、葬儀や法事による遺族に対するグリーフケアの重要性について指摘してきた。葬儀や法事からグリーフケアの機能が失われてきたことが、いわゆる葬式仏教と世間で揶揄されるようになった元凶の一つになっていると受け止めている。
葬式・法事は、亡くなった「おくられびと」の供養の場であると同時に、「おくりびと」のグリーフケアの場であることを、今回の震災を通じて私自身あらためて実感したところである。
ご家族を失い、深いグリーフを抱えている方にとって、回復へのプロセスの最終段階が、亡くなった方との関係性の再構築だと私は捉えている。眼前から消えてしまった肉体のないいのちと、どのようにつながりを感じることができるのかが、その際の重要なポイントである。宗教者には、そのコーディネーターとしての役割が求められているのであろうし、それはまさに宗教者にしか務まらない役割でもあろう。
そのためには、まず、宗教者自身がしっかりとした死生観や来世観を持つことが必須である。仏教は釈尊以来、輪廻や輪廻からの解脱を説く。あるいは往生について語るようにもなった。宗旨によりさまざまな捉え方があり、答えは一様でないだろう。自分自身で腑に落ちた答えを持っておくことが肝要だ。
しかし、たとえしっかりとした死生観や来世観を持っていても、それを決してグリーフを抱えている人たちに押しつけてはならない。
被災地を巡っていると大人や子どもから「和尚さん、人は死んだらどこへ行くんだろう?」という問いをしばしば投げかけられる。そのようなとき、まず私は「あなたはどう思うの?」と聞き返す。
東北の方々は信仰に篤い人が多い。それは必ずしも特定の宗教や宗派ということではなく、東北の地で連綿と伝えられてきた、仏教とも神道とも言えぬ土着の信仰が息づいているということであろう。たとえば漁師の方々は、海へ漁に出る前に安全祈願や豊漁祈願のためにお寺や神社に詣り、漁から戻って来ると収穫した魚をまた納めに訪れる。日常の中で生活と一体となった信仰の有り様がそこにはある。
私は、「死んだらどこへ行くのか」という問いに対して、まず、それぞれの死生観や来世観について確認し、それを優先させるように努めている。決して信仰の押しつけはしない。それは、問いかけをする方の中に、すでに漠然としながらも答えがある場合が往々にしてあるからだ。東北の方々に限らず、日本人の多くが死後「無」になるとは考えない。目には見えなくとも、亡くなった方の「何か」が死後も存在し続けると感じている人が多い。それは日本人特有の霊魂観と言ってもよいだろう。私たち宗教者は、その答えを確認するための触媒になればよいと思う。
しかし、宗教者自身が信ずる答えを持っていないと、その触媒になることがむずかしくなる。問われた方が動揺してしまっては、問うた方も不安になる。結果、精神的により不安定な状況を生み出しかねない。
漠然とした答えが、その方々の中で確かなものになったとき、彼岸と此岸のいのちはしっかりとつながり、揺るぎのない関係性が再構築される。宗教者によるグリーフケアの役割がそこにある。
冒頭で述べたように、ご遺族の悲嘆感情が癒されるまでには、まだまだ時間がかかるに違いない。別れの準備の時間がまったくなかった災害時にあっては、当然ながらより多くの時間が必要となろう。
しかし、それでも人間は回復する力を持っている。宗教はその力をより促進することができる。人と宗教の力を信じつつ、五年、十年、二十年と、良き伴走者として、被災した方々のそばに寄り添い続けていきたいと思う。