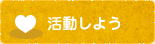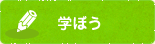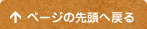仏教者の活動紹介
子どもとともに半世紀 ―長伝寺 木村敦子師―
(ぴっぱら2003年7月号掲載)
地域に溶け込んだ寺
気の早い台風が日本列島を駆け抜けていった日。「七里の渡し」とそこでとれる蛤で有名な城下町・三重県桑名市から、雨に洗われた街並みを抜けると、住宅街の向こうに黄金色の畑が見えてきた。「麦秋」という言葉の意味を実感する光景の中に、親鸞聖人の像が立つ境内がある。浄土真宗本願寺派の長伝寺は、静かな街に溶け込んでいた。
学校の完全5日制で休日となった土曜日の午前8時。学校よりも早い時間にもかかわらず、本堂には子どもたちが集まっていた。小学校1年生から6年生までの子どもたちが、自分で長机を支度する。やがて年長の女の子が交代で奏でる伴奏のオルガンに合わせ、賛歌を歌って会が始まる。みんなで名号を唱え、お話を聞いた後、ご本尊に向かって正信偈を読む。
きちんと正座してまっすぐに経本と向き合う子。どこを読んでいるのかわからなくなって周囲を見回す子。落ち着かなくてじっと座っていられない低学年の男の子を、姉らしい年長の女の子が諭している。そんな光景は、今も昔も変わらないようだ。
子どもたちを見守りながら一緒にお経を読み、子どもたちに「先生」と呼ばれているのが、前坊守の木村敦子さんだ。80歳の誕生日を迎えた今も、子どもたちとともにご本尊に手を合わせる。
女性として 住職として
住職だった夫が亡くなったのは、木村さんが29歳のとき。だが、ただ悲しみに暮れているわけにはいかなかった。寺の仕事は待ってくれない。義父は72歳と高齢で、息子はまだ4歳だ。自分がやるしかないと思い定め、大急ぎで得度した。
「事情が事情だから、採点を甘くしてくださったんでしょう」とご本人は謙遜するが、受かるまで何年もかかる人もいるという宗門の教師資格試験(住職になるために必要な資格試験)に一回で合格し、住職を継いだ。先々代である義父に教えられながら、息子が高校を卒業するまでの十数年間、とにかく夢中で法要やお参りを勤めた。
終戦してまだ10年も経っていない頃の話だ。女性が表立って働き、住職として勤めることはかなり珍しかった。さぞかし苦労があったことと思いきや、「大変だったこともありますけれど、もう忘れてしまいました。楽天家なんです」と微笑む。
とはいえ、「泣きながら本堂の掃除をしたことも」あったと言うが、「義父が後ろ盾になってくれましたし、門徒の方々にもよくしていただいた。すべてほとけさまのお力ですね」と言い切る。その芯の強さは、そのまま信仰の深さであるようにも感じられた。
子どもたちに育てられて
生まれ育った実家は真宗高田派の寺だったという木村さん。実家の父が自坊で日曜学校を開いていたこともあって、子どもの頃からほとけさまに近づき、教えに触れることの大切さを感じていた。そこで、寺を引き継ぐのと同時期に日曜学校を開設。以来50年、半世紀という長きにわたって、絶えることなく続けてきた。
開設当初は、子どもたちの楽しみが少なかった時代でもあり、多いときには80人もの子どもたちが寺に集まった。歌を歌ったりお経をあげたりといった、今も変わらない日曜学校を行う一方で、紙芝居やゲームをしたり、幻灯の上映をしたり、バスを仕立てて潮干狩りに行ったこともあった。
「今思うと、『よくまあやっていたな』と思うこともありますが、やはり若かったので夢中だったんですね。何よりも、子どもたちに助けられ、育てられたと思っています。親御さんたちもよく任せてくださいました」
しかし、時代が進むにつれ、塾や習い事、少年野球などで子どもも忙しくなった。集まってくる子どもたちは次第に減っていく。本堂の隅に作られている文庫の児童書に読みふけったり、走り回って遊んだりと、多くの子どもが出入りしていたのが、4、5人、時には1人しか来ないこともあったという。そんなふうに子どもの人数が減ると、それを機に日曜学校をやめてしまう人が多いが、木村さんはやめようとは全く考えなかった。
やがて、子どもが友だちを連れてきたり、兄弟が来るようになったりして、今では30人以上の子どもたちが毎週集まってきている。かつてのように長居する光景はなくなったが、「それでも毎週来てくれているのは、やはりほとけさまのお力ですね」と木村さんは語る。
一方、子どもを送り出している親たちも、かつては自分もお寺に通っていたという人が多い。今では、そんな「卒業生」たちの手で、お寺のさまざまな行事も運営されている。
変わるもの 変わらないもの
現在、毎週土曜日の「日曜学校」の他、1月の報恩講、5月の親鸞聖人降誕会など、節目ごとに行事を行っている。降誕会では、子どもたちは1カ月あまりも練習を重ねて劇や踊り・歌を披露する。また、前年の降誕会から1年の間に生まれた子どものための初産式も併せて行っていて、子どもがテーマの一日だ。
中でも子どもたちが楽しみにしているのが、8月のキャンプだ。「これに来たくて日曜学校に参加している子もいる」というほどの人気なのだという。自分たちで食事を作り、肝だめしや花火大会をした後は、本堂で枕を並べて眠る。今も昔も変わらない夏の風物詩だ。
近年、子どもが変わったと言われているが、50年の間子どもたちを見てきた木村さんは、必ずしもそう感じてはいないようだ。
「確かに、昔の子どものほうがよく暴れましたね。テレビゲームが流行るようになった頃からは、日曜学校でも、すっと来てさっと帰ってしまいます。それでも、年上の子が年下の面倒を見ることは変わりませんし、お菓子があればみんなで分け合って食べてますよ」
表面の変化にとらわれずに子どもの本質を見つめ、半世紀の経験を重ねてきた人だけが持つ、深いまなざしを感じる言葉だった。
引き継がれる思い
息子が住職を引き継ぎ、若坊守とともに寺務をとりしきっている今も、時折、頼まれて木村さんが自ら法要を勤めることがあるという。日曜学校も、「体の動く限り」木村さんが続けていくつもりだそうだ。
「私にも曾孫がいるんですよ」と目を細めて語る笑顔は「どこにでもいる優しいおばあちゃん」なのに、その細い身体には、法要に日曜学校にと動き続ける体力と精神力がひそんでいる。
それでも、かつて病気で1カ月入院したことがあったという。その間は住職が日曜学校を見てくれていたそうだ。また、3人いる孫のうちの1人が龍谷大学に在学中で、日曜学校をテーマにレポートを書くなど、寺や子どものことに関心が高く、子ども好きなのだと嬉しそうに語ってくれた。「孫はスポーツが得意なので、そんな方面で、これまでと違った形ででも学校を続けてくれれば......と思っているんですよ」と顔をほころばせるのは、自分の思いが、そしてほとけの教えが次代へと引き継がれていくことへの喜びなのだろう。
それは寺の中にとどまらず、つたない口調でも熱心にお経を読んでいた子どもたちにも引き継がれ、着実に人々に伝わっているに違いない。教えが広がっていくのを見る喜び。それもまた、木村さんの顔をほころばせているのかもしれない。(内)